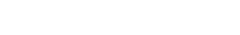(有)十和田湖樹海農園 代表取締役社長「宮館文男」
小坂七滝ワイナリーで生産するワインのほとんどの原料(ぶどう)は鴇地区の十和田湖樹海農園から供給を受けています。
小坂町のぶどう栽培は、昭和63年(1988)利用していない農地活用のため、鴇(ときと)地区で始まりました。
鴇地区の標高は約300m、太古に十和田湖の大噴火によって堆積した火山灰土壌で水はけが良くぶどう栽培に最適な環境でした。冷涼な土地でも栽培が可能で病害の少ない「山ぶどう」交配品種を導入しました。
現在、小坂七滝ワイナリーで生産するワインのほとんどの原料(ぶどう)は鴇地区の十和田湖樹海農園から供給を受けています。
(有)十和田湖樹海農園 代表取締役社長が「宮館文男」氏です。 栽培面積:約7ヘクタール(生食用品種含む)、ワイングランド:2.2ha、小公子:1.5ha、岩木やまぶどう:0.1ha、その他:3.2ha 生産量:約33トン~35トン

長く収穫ゼロの
年が続く
栽培を「平成元年」からスタートしましたが、まさしくゼロからのスタートで「平成8年」までは苦労の連続でした
山ぶどう研究の第一人者で日本葡萄愛好会創始者の故・澤登晴雄氏(1916~2001年85歳没)から分けて頂いた「山ぶどう」交配品種のなかでも代表的な「小公子」「ワイングランド」で栽培を「平成元年」からスタートしましたが、
まさしくゼロからのスタートで「平成8年」までは苦労の連続でした。
「宮館文男」が陣頭指揮をとり、生産者が力を合わせて、ぶどう栽培に没頭するのですが、花は咲くのですが、実が付かない年が何年も続きました。栽培技術の未熟さから何がいいのか?悪いのか?も判断ができず、途方に暮れていました。
そんな時に手を差し伸べてくれたのが秋田県横手市のぶどう生産農家さんや秋田県果樹試験場の皆さんでした。
ご指導に沿って栽培技術の体系の見直しを図ったところ、徐々に成果が表れるよになりました。「平成10年」、10年目にして初めて満足のいく結果が出ました。

十和田樹海農園のぶどう栽培の特徴
「宮館文男」が他のぶどう栽培農家さんを束ねて、生産計画や出荷計画を立てます。まさにぶどう栽培の司令塔
鴇地区の十和田湖樹海農園では「宮館文男」が他のぶどう栽培農家さんを束ねて、生産計画や出荷計画を立てます。まさにぶどう栽培の司令塔になっています。
十和田樹海農園では当初新しい技術としてヨーロッパスタイルの垣根仕立てで栽培していましたが、「山ぶどう」交配品種の特性が理解出来たことで、日本式の棚仕立てに変更をしました。
ぶどうの葉が太陽にあたる面積を最大限に大きく出来ることで、小坂町のような冷涼な気候でも、ぶどうの完熟を促す工夫がされています。 鴇地区の山ぶどうはまさしく「ワイン」専用に栽培されていて、品種ごとに開花から収穫までの日数がおおよそわかっているので、その時期を見極め、収穫日を決定し、天候の予報などにより収穫時期の調整をします。
手間を惜しまず、一房一房、丁寧に手摘みされていますので、人がぶどうの状態を見ながら収穫するため、腐敗果や未成熟果の混入を未然に防ぎ、高品質なワイン用のぶどうが収穫されています。

【剪定(11月~12月)】
雪の多い小坂町ですので、棚に雪が積もりにくい状況にするため、11月から剪定が始まります。1本1本前年の樹勢を確認しながら、来年の芽の数を決め慎重に剪定を行います。
【展葉(5月上旬)】
サクラが見頃を迎える季節になりますと、ぶどうの芽が膨らみ今年の葉が開いてきます。まるで花が咲いたように農園全体が明るく鮮やかになり、秋の実りが待ち遠しい季節が訪れます。
【開花(6月下旬~7月上旬)】
開花の季節。気候が穏やかで太陽をいっぱい浴び、結実が良くなるように祈ります。1年の中で一番大切な時期。雨が多くなったり、低温がこの時期の大敵です。
【果実肥大期(7月~8月)】
開花期の気候が温暖であれば生育が順調に進み、果実が地下から養分をたくさん吸い上げて、果実が肥大していきます。
【果実着色期(8月中旬~9月)】
夏の十分な日照と地下からの養分で肥大した果実が、色付きはじめる季節。適正な葉数の確保と枝の伸びを抑えることで、着色促進と糖度上昇を促すことが重要になります。
【収穫期(9月上旬~10月下旬)】
果実の収穫が一斉にはじまる季節。「小公子」九月上中旬収穫、「ワイングランド」十月中下旬収穫、「岩木山葡萄(いわきやまぶどう)」十月下旬収穫。
【落葉期(11月~12月)】
果実の収穫が終わり、樹々も農園もやっと一息つく季節。樹々の枝の中の養分(樹液)が越冬のため地下の根に降りると落葉が始まり、ぶどうの休眠期に入ります。
小坂七滝ワイナリー
「今後の展望」
「山ぶどう」系品種にこだわり、ワイナリーを応援し、一般ユーザーに価値をアピールしていきたい
「山ぶどう」交配品種にこだわり、「山ぶどう」交配品種で生産される小坂ワインを応援し、同時に一般ユーザーに価値をアピールしていきたいと考えています。
山ぶどう交配品種は奥が深く、益々研究を重ね、品種改良と栽培経験を積み、小坂産ぶどうとワインの評価を確固たるものにしていきたいと考えています。